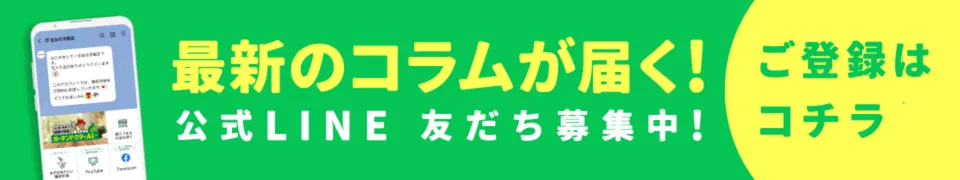目次
知っておきたい園芸情報 - 園芸知っトク情報パプリカとは~ピーマンとの違いや、育て方、簡単レシピ~

ピーマンは栽培が比較的簡単な植物ですが、ピーマンによく似たパプリカは栽培難度が高めです。しかし栽培のポイントを押さえれば、パプリカも十分に育てることができます。
本記事では、パプリカの特徴やピーマンとの違い、基本的な育て方や育てる際の注意点、簡単レシピを紹介します。
パプリカの特徴
パプリカは赤や黄、オレンジなどカラフルな見た目からカラーピーマンと呼ばれることもある植物です。ピーマンと比べると収穫までに時間がかかることなどから、ピーマンの栽培よりも難しいとされています
パプリカとピーマンの違い
パプリカとピーマンは色以外にどのような違いがあるのでしょうか。ピーマンもパプリカも、生物分類としてはナス科トウガラシ族です。ピーマンは食べると独特の苦みがありますが、パプリカは苦みがなく果物のような甘みがあり、サラダなど生食にも向いています。また、栄養価はパプリカのほうが高めです。
パプリカの育て方

パプリカをプランターで栽培する際の基本的な育て方を紹介します。
◇事前準備
パプリカは根が深く張るため、深さ30cm以上のプランターを用いるのがおすすめです。土は野菜用培養土を使うと、手間がかかりません。土に元肥が入っていない場合は、「マイガーデン元肥用」などの化成肥料を土に混ぜるようにしましょう。「マイガーデン元肥用」はじっくり効き続けるため、元肥として使いやすい便利な肥料です。
◇苗の選び方
パプリカを種から育てるのは、ただでさえ難易度が高めのパプリカの栽培難度がさらに上がってしまいます。そのため、苗から育てるのがおすすめです。苗は、本葉が10枚くらい付いている丈夫なものを選びましょう。若すぎる苗や、1番花に実が付いているような老化した苗は、生育がうまくいかない可能性があります。
◇植え付け
パプリカは低温に弱いため、植え付けは5月上旬~6月上旬が適しています。苗の根を傷付けると病気になったり枯れたりするため、取扱いに注意しましょう。また、株の間隔が狭いと日光が十分に当たらなくなるので、間隔は十分に空けてください。植え付け後に気温が低くなったときは、ビニールトンネルなどで保温してやります。
5つのパワー成分が配合された「X-ENERGY(エックスエナジー)」を使えば、寒さや日照不足などのストレスに負けない丈夫な株に育ちやすくなるため、おすすめです。
◇支柱立て
パプリカは茎が細くて倒れやすいため、支柱を立てて誘引しなければなりません。高さが約100cmまで生長することを考慮すると、地面へ刺す部分の長さを加えた120cmくらいの長さの支柱が2~4本必要です。
おすすめの3本立ての場合、用意した支柱3本をクロスさせた状態で立てて茎を結びます。茎を結ぶ際は輪を大きめにして、生長を妨げないようにしましょう。
◇整枝
植え付けから1~2ヵ月で1番花が咲きます。これに実が付くと株の生長が悪くなるため、1番花は摘み取ります。また、1番花の下から出てくる脇芽を生長させると、葉が混み合って害虫が発生しやすくなるので、必要な脇芽以外を摘み取る「芽かき」もしなければなりません。
スペースがある場合は、メインとなる枝に加えて脇芽を2本育てていく「3本仕立て」で育てるのがおすすめです。ベランダなどスペースが限られる場合は、主枝+脇芽1本の「2本仕立て」がよいでしょう。
◇追肥
パプリカは、一般的に実を多く付けるため肥料切れを起こしやすい植物です。また、実が完熟するまで時間がかかることから、パプリカの実1個でピーマン3~4個分の肥料が必要とされています。
実が付き始めたら肥料を与えます。固形肥料は2週間ごと、液体肥料なら1週間ごとの施肥が必要です。固形肥料を株の根もとにまくと障害が起こるケースがあるため、根もとよりも外側にまくようにします。
◇収穫
実の色が赤・黄・オレンジ色に変わり、完熟する頃合いが収穫のタイミングです。実が付いてから完熟までは約3週間かかります。その間に雨に当たりすぎると実が傷むため、ビニールなどをかぶせて雨よけにするとよいでしょう。
また、すべての実を実らせると栄養不足になる可能性があります。最初にできた実はすぐに摘み取って、株の生長を優先したほうがよいでしょう。生長後も実の数が多すぎるようであれば、適宜摘み取って調整します。
パプリカを育てる際の注意点

パプリカを育てる際には、いくつか押さえておいたほうが良いポイントがあります。そのため、ここでは育てる際の注意点を解説します。
◇栽培環境
パプリカは日光がきちんと当たる場所で栽培しましょう。日照不足だと実が育ちにくくなるためです。また、乾燥や過湿に弱いため、対策が必要です。エアコンの室外機の風が当たる場所などは避けるほか、保水性・排水性が良い土を使って乾燥・過湿を防ぎましょ
◇水やり
パプリカの水やりの仕方は、株の生長によって変わります。植え付け直後は水やりを控えましょう。そうすることで根が地中に張りやすくなります。株が生長すると水が不足しがちになるため、しっかりと水やりをしてください。
水やりの量は、土の表面が乾いたらプランターの底から水が流れ出る程度です。気温が高い時期は、日中に水やりをすると根腐れになるケースがあるため、朝や夕方の涼しい時間に行ないます。
◇おもな病気
パプリカがかかりやすい病気は、うどんこ病や灰色かび病などです。うどんこ病は水やりの際の水はねが原因になるケースがあるため、マルチングで泥はねを防ぐとよいでしょう。また、風通しの悪さも原因になることから、葉の整理も大切です。
さらに、パプリカは尻腐れ症を起こすことがあります。尻腐れ症とは実のお尻部分が黒ずみ、最終的には陥没する症状です。一度発生すると元に戻らないため、見つけたら実を摘んで廃棄します。
尻腐れ症の原因の一つは、水やり不足などによるカルシウム不足です。「トマトの尻腐れ予防スプレー」を使えばカルシウム欠乏を解決できるため、ぜひ利用してみてください。
◇おもな害虫
パプリカに付きやすい害虫はアブラムシやハダニです。数が少ないうちであれば、アブラムシはセロハンテープで、ハダニは水をかければ駆除できます。数が増えてきたときは薬剤をまいて対応しましょう。
◇連作障害に注意
パプリカはナス科で、連作障害が出やすいため注意が必要です。連作により尻腐れ症も発生しやすくなります。過去3~5年でナス科の植物を植えたところにパプリカを植えないようにしましょう。
◇健康状態の判断方法
パプリカはめしべよりもおしべが高い状態が正常です。おしべとめしべの高さが同じのときや、おしべのほうが高いときは健康状態が良くありません。追肥をしたり日当たりを変えたりする必要があります。
また、株の先端にある「生長点」から近いところに花が咲いた場合も栄養不足です。逆に成長点から遠すぎるところに花が咲くと、茎が必要以上に間延びした「徒長(とちょう)」状態のため注意しましょう。生長点から10~20cmくらいが健康な開花位置です。
パプリカの食べ方と簡単レシピ
パプリカはピーマンと異なり、加熱調理だけでなく生食にも向いている食材です。そのため、カラフルな見た目を利用して、食欲をそそる料理に仕上げるような使い方が可能です。ただし、熱に弱い栄養素ももっているため、加熱しすぎに注意しましょう。
パプリカのみずみずしさや甘さを簡単に楽しめるレシピとして、「パプリカの浅漬け」があります。材料と作り方は以下の通りです。
【材料】
● パプリカ 2個
● だし汁 200ml
● しょうゆ 大さじ2
● 酢 大さじ2
● 塩 小さじ1
【作り方】
1. チャック付きポリ袋にだし汁、しょうゆ、酢、塩を入れる
2. パプリカを一口大の乱切りにする
3. だし汁を入れたチャック付きポリ袋にパプリカを入れて軽くもみこむ
4. 冷蔵庫で2時間以上漬ける
5. 汁気を切って皿に盛る
まとめ
パプリカはピーマンとよく似た植物ですが、収穫まで時間がかかることなどから栽培難度は高めです。特に、実が付いてから完熟まで約3週間かかるため、雨に当たりすぎないようにする対策などが必要です。また、トマトの尻腐れ予防スプレーなどを活用して尻腐れ症の発生を防ぎましょう。
ポイントを押さえれば、パプリカの栽培も決して困難ではありません。本記事を参考にパプリカ栽培のポイントを理解し、ぜひ挑戦してみてください。
パプリカとは~ピーマンとの違いや、育て方、簡単レシピ~園芸知っトク情報のページです。
KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。
商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。