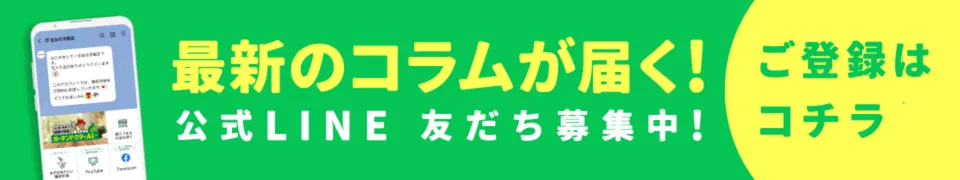知っておきたい園芸情報 - 園芸知っトク情報夏に強いケイトウの育て方・栽培方法!種類や害虫対策、栽培スケジュールを紹介!

ケイトウは、夏から秋にかけて、炎のような形状と色合いの花を咲かせます。その見た目にちなみ「燃える 」を意味するギリシャ語から、学名「セロシア」と名付けられています。華やかさと栽培のしやすさから、多くのガーデナーに親しまれている植物です。
本記事では、ケイトウの特徴や種類、大まかな栽培スケジュール、育て方、気を付けたい病害対策について詳しく解説します。
ケイトウの種類や特徴について

ケイトウにはどのような特徴があるのでしょうか。ここではケイトウのグループ分けや代表的な品種と併せて紹介します。
◇ケイトウの特徴
ケイトウは、ヒユ科ケイトウ属に分類される植物で、炎やニワトリのトサカに似た形状の赤や黄、オレンジなどの花を、夏から秋にかけて咲かせるのが特徴です。名前の「ケイトウ」も、ニワトリの頭(鶏頭)に由来しています。
日本では観賞用として栽培されるほか、切り花やドライフラワー の用途で栽培されています。
暑さに強く一度咲くと花持ちが良いため、比較的栽培しやすい植物です。一方で、寒さに弱く冬には枯れてしまうため、国内では一年草として扱われています。そのため、毎年花を楽しむには、種から育て直す必要があります。
◇ケイトウのグループ分け
ケイトウは、花穂の形状などからおもに次の5つのグループに分けられます。
・トサカ系、クリスタータ
ケイトウのなかで最も一般的な種類です。花穂は、ニワトリのトサカのように、扇状・帯状のかたちをしています。
・久留米ゲイトウ
トサカ状の花が球状にまとまって咲くのが特徴で、分枝せず 大輪に育ち やすいため、存在感があります。花弁はビロードのような質感が特徴で、茎が長いため切り花にも適しています。
・プルモーサ系、羽毛ケイトウ
名称のとおり、羽毛のような見た目をした柔らかい円錐形の花穂を持つのが特徴です。
・キルドシー系、ヤリゲイトウ
槍のように先が尖った花穂を持つのが特徴です。同じく直立型のプルモーサ系よりも、ややシャープな形状をしています。
・ノゲイトウ
花穂が長い円錐形で、枝分かれします。ほかのグループのようにトサカ状に広がることはありません。全体的に乾燥した質感で、草丈が長く吊り下げやすいため、ドライフラワーに向いています。
◇ケイトウの代表的な品種
ケイトウの代表的な品種には「キャッスル」や「キャンドル」などが知られています。
キャッスルはプルモーサ系の品種で、上向きに立った花の先端は、名前のとおり城の尖塔を連想させる姿をしています。
ノゲイトウ系の品種で代表的なのが、キャンドルです。花はろうそくの炎のような見た目をしており、草丈が2m近くまで成長することもあります。成長とともに倒れやすくなるので、支柱で支えると安心です。
このほかにも、「ホルン」や「アーリーローズ」など多彩な品種があり、色や草丈もさまざまです。植える場所や広さ、用途に合わせて選ぶとよいでしょう。
ケイトウの栽培の流れ

ケイトウは次のスケジュールを目安に栽培を行ないます。
| 作業 | 適期 | 説明 |
| 種まき | 4月下旬~6月中旬(遅まきの場合は8月~9月中旬頃) | 発芽適温は20~30度。遅まきの場合は草丈が抑えられ、コンパクトな株で秋咲きを楽しめる。 |
| 植え付け・定植 | 5月~7月( 暖地は9月も) | ポット育苗後、苗の本葉が3~5枚に育った頃に移植 する。 |
| 肥料 | ― | 鉢植えやポット栽培の場合は、本葉が3~4枚出始めたら液体肥料を使用する。 |
| 開花 | ― | 種まき後およそ2ヵ月で開花が始まり、6月下旬~11月頃まで長期間楽しめる。 |
ケイトウの基本的な育て方のポイント

ケイトウは初心者でも栽培に失敗しにくい植物ですが、あらかじめ育て方のコツを押さえておくことで魅力をより引き出すことができます。
ここでは、ケイトウを育てる際のポイントについて解説します。
◇日当たりや土壌
ケイトウは比較的丈夫な植物ですが、過湿による根腐れには注意が必要です。栽培環境が悪い場合には、初期段階で立枯病が発生する恐れもあります。植える際は、一日を通して日が当たり、水はけの良い土壌を選んでください。
庭植えの場合、肥料はほとんど必要ありません。土質をあまり選ばない植物ですが、土が肥えすぎていると葉ばかりが茂ってしまい、花とのバランスが崩れることもあります。そのため、やや痩せた土のほうが、花姿が整いやすくなります。
◇種まき
ケイトウの発芽適温は25度前後のため、種まきは4月中旬〜6月頃が適期です。花芽は日照時間が短くなる頃に形成され始めるため、株を大きく育てたい場合は5月までに種をまき終えるとよいでしょう。
また、根を触られるのを嫌う性質があるため、定植後に根を痛めないよう、最初から大きめの鉢や花壇に直まきするのが安心です。
発芽までは、5〜7日程度かかります。
◇植え付け
植え付けを行なう場合は、一般的には5月〜7月頃、本葉が5〜6枚に育ったタイミングが適期です。苗がしっかり育ってから植えることで、根付きやすくなります。
風通しと生育スペースを確保するため、株間は広めに取りましょう。比較的小型の矮性品種であれば10~20cm、分枝の多い大型種では30~40cmほどの間隔を空けるのが理想です。
◇水やりと肥料
土が乾かないように、毎日たっぷりと水を与えましょう。特に種まき後から苗が育ちきって 根がしっかり張るまでは、土を極端に乾燥させないよう心がけてください。乾燥が進みやすい夏場は、朝夕2回に分けて水やりしてもよいでしょう。
特に鉢植えは水切れしやすいため、乾燥状態をこまめに確認する必要があります。
また、鉢植えの場合、本葉が3〜4枚出始めたら、液体肥料を週1回 与えましょう。保水性を向上させる効果のある 「マイガーデン液体肥料」がおすすめです。
日照不足や生育不良が気になる場合は、活力液「X-ENERGY」の活用も効果的です。植物の発育をサポートする成分が配合されており、液体肥料と併用できます。
◇その他の作業
分枝が多い品種は、草丈が20~30㎝ほどに伸びた頃に摘心や花がら摘みを行なうと、脇芽がよく育ちます。株姿が整い、花数も増えやすくなるため、生育の様子を見ながら取り入れるとよいでしょう。
また、草丈の高い品種は、成長の途中で自重を支えきれずに倒れてしまうことがあります。蕾が出始めたら支柱を立てるか、株元に土寄せして倒れないようにしましょう。
ケイトウの種の増やし方
ケイトウは暑気に強いため、夏越しの対策は特に必要ありません。一方で、生育に適した温度の下限が15度のため、国内ではほとんどの地域で冬を越せません。ただし、室内で温度管理を行なえば、秋に植えた株も冬の手前まで花を楽しむことができます。
また、ケイトウは自家採種が可能です。咲き終わったあとの乾燥した花から種を取り、乾燥させて春まで保存すれば、翌年の種まきに使うことができます。花がらを摘まずそのまま残しておいた場合は、こぼれ落ちた種から自然に発芽することもあるでしょう。
種を採取したい花はあらかじめ袋をかけておくと、交雑を防ぎつつ、種の管理がしやすくなります。
ケイトウの害虫対策
ケイトウは、「線虫(センチュウ) 」が付きやすいため、発生を抑えるために連作はなるべく避けましょう。このほかにも、ヨトウムシ・ズイムシによる食害や、乾燥によるハダニ、アブラムシの発生もよく見られます。日々状態を観察しながら、定期的に殺虫剤を散布しておくと安心です。
ケイトウ向けの殺虫殺菌剤は、「ベニカナチュラルスプレー」をおすすめします。厳選された 3つの天然由来成分で、ヨトウムシやアブラムシ、ハダニの卵までしっかりと防いでくれます。
まとめ
ケイトウは、鮮やかな花姿を長く楽しめる一年草です。日当たりと水はけの良い環境さえあればよく育つため、園芸初心者でも安心して栽培に挑戦できます。
品種によっては摘心や支柱立てなどの手入れが必要ですが、ポイントを理解したうえで適切に育てることで、草丈や花形のそろった美しい姿を楽しめるでしょう。また、害虫への対策を施すことで健康的な状態が長持ちします。
遅まき栽培などを取り入れることで開花の時期も調整したり、さまざまな品種や育て方を試したりしながら、ケイトウの栽培をより長く楽しみましょう。
夏に強いケイトウの育て方・栽培方法!種類や害虫対策、栽培スケジュールを紹介!園芸知っトク情報のページです。
KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。
商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。