目次
知っておきたい園芸情報 - 園芸コラムバラの病気一覧!病気にかかったときの治療と予防方法
バラを育てていると、葉っぱや花に斑点があらわれ、変色などの異常が見つかることもあります。こうした異常は、バラが病気にかかったサインかもしれません。
異常を見つけたら早めに対処しましょう。早期に発見できれば対処も簡単に済み、被害を最小限に抑えられます。
この記事では、代表的なバラの病気について、症状や発生原因、治療・予防方法などを解説します。自宅でバラを育てている方は、ぜひ参考にしてください。
代表的なバラの病気
まずは、代表的なバラの病気と症状、発生しやすい時期について解説します。
病気にかかると、葉っぱや花の色が悪くなって美観を損なうだけでは済まないこともあるため注意しましょう。花が咲かなくなったり、葉っぱが落ちて枯れたりする可能性もあり、早急な対処が必要です。
【バラの代表的な病気】
-
うどんこ病
-
黒星病(黒点病)
-
さび病
-
灰色かび病(ボトリチス病)
-
ベト病
-
枝枯病(キャンカー)
-
根頭がん腫病
それではより詳しく症状の特徴などをみてみましょう。
うどんこ病
症状
|
症状 |
葉っぱや蕾、新芽などのやわらかい部分が白っぽい粉を吹いた状態になり、生育を阻害します。 |
|
原因 |
風で運ばれるかびの胞子が原因でかかる病気です。風通しの悪い環境でかかりやすい傾向があります。 |
|
発生しやすい時期 |
4~11月に発生しやすく、特に一日の寒暖差が大きい5~7月や9~10月に多く見られます。 |
|
対処法 |
白くなった部分を取り除き、薬剤を散布して治療します。 |
うどんこ病にかかると、葉っぱや蕾、新芽などバラのやわらかい部分が白っぽくなって広がり、うどん粉をまぶしたような白い粉ふき状態になります。白い粉のように見えるものはかびの一種です。
うどんこ病にかかると葉っぱなどが萎縮し、バラの成長を阻害します。風で運ばれたかびの胞子が付着して感染するため、風通しの悪い環境で発生しやすい特徴があります。
薬剤をまいて治療しますが、被害が大きい・治まらない場合は、白くなった葉っぱをすべて取り除き、枝葉を整理したうえで薬剤をまきましょう。
黒星病(黒点病)
|
症状 |
葉っぱに黒い斑点ができて黄色く変色し、葉っぱが落ちて生育を妨げます。 |
|
原因 |
土のなかにいる病原菌が原因です。水の跳ね返りで葉っぱに菌が付着して感染します。 |
|
発生しやすい時期 |
4~11月に発生します。特に暖かくて雨の多い時期である、6~8月上旬や9月下旬~10月中旬に多くなります。 |
|
対処法 |
斑点が出た葉っぱは取り除き、薬剤を散布して治療します。 |
黒星病は黒点病ともいい、葉っぱに黒や淡褐色の斑点ができます。斑点が広がると、やがて黄色く変色して葉っぱが落ちてしまい、バラの成長を阻害します。花が咲きにくくなるほか、若い枝に黒いあとが残ることもあり、バラの状態を美しく保てません。
黒星病の病原菌は土のなかや、病気にかかって落ちた葉っぱに潜んでいます。水の跳ね返りで下方の葉っぱに付着して感染するため、雨の続くシーズンや湿度の高い環境で多発、拡大しやすいです。
水の跳ね返りに注意し、病気にかかった葉っぱは速やかに取り除いて感染拡大を防ぎましょう。黒星病にかかったあとに出た新芽には、予防薬を散布して再発を防ぐことも大切です。
さび病
|
症状 |
葉っぱにイボ状のものができ、なかからサビに似た赤褐色の粉が出ます。 |
|
原因 |
病原菌の胞子が繁殖して発生する病気です。 |
|
発生しやすい時期 |
4~11月に発生し、特に雨が多くなる4月上旬~6月下旬や9月下旬~11月上旬に多くなります。 |
|
対処法 |
症状の出ている箇所を取り除き、薬剤を散布して予防します。 |
さび病は、葉っぱにできたイボ状のものが褐色の斑点になり、なかからサビに似た赤褐色の粉が出る病気です。症状がひどいとサビ状の粉が葉っぱを覆い、バラが枯れる可能性もあります。
蒸れやすい環境だと病原菌となる胞子の繁殖が促進されるため、湿度を抑えましょう。症状が見られたら、被害箇所を取り除き、薬剤をまいて予防します。
灰色かび病(ボトリチス病)
|
症状 |
進行すると花びらなどが灰色の斑点(かび)に覆われ、花が咲かなくなります。 |
|
原因 |
ボトリチス菌に感染して発生し、アザミウマの食害から菌が侵入することもあります。 |
|
発生しやすい時期 |
3~12月に発生します。特に低温多湿で日照時間の短い4~7月や10~11月に多い病気です。 |
|
対処法 |
症状の出ている蕾や花びらを取り除き、薬剤を散布します。アザミウマの食害があるなら退治しましょう。 |
灰色かび病(ボトリチス病)は、進行すると感染箇所が灰色の斑点(かび)に覆われる病気です。バラの花びらに感染すると、まず赤や白の斑点があらわれます。症状が出た花は咲かずに蕾のまま腐ってしまうため、バラの花を楽しめません。
ボトリチス菌への感染で発生し、湿度が高く、風通しの悪い環境下では発生リスクが高まります。また、アザミウマが花や蕾を食べたあとから病原菌が侵入することもあるため、アザミウマを見つけたら早急に退治しましょう。
感染が確認されたら、症状が出ている蕾や花びらを取り除き、薬剤をまいて治療します。
ベト病
|
症状 |
若葉に斑点、葉裏にかびの菌糸があらわれて葉っぱが落ちます。 |
|
原因 |
土のなかにいる病原菌が水の跳ね返りで葉っぱに付着して感染します。 |
|
発生しやすい時期 |
4月下旬~11月上旬に発生します。特に梅雨や秋の長雨シーズン(5月下旬~7月上旬・9月下旬~10月)に多い病気です。 |
|
対処法 |
症状の出ている葉っぱを取り除き、薬剤を散布します。 |
ベト病はバラの若い葉っぱに淡褐色や淡黄色の斑点、日やけしたようなシミが広がる病気です。葉っぱの裏にはかびの菌糸があらわれて葉っぱが落ち、バラの生育を妨げます。被害が大きいとバラが枯れる可能性もあるため、注意が必要です。
ベト病に原因は、土のなかにいる病原菌です。跳ね返った泥水を介して葉裏に付着して感染し、風通しが悪く、蒸れやすい環境で起きやすい傾向があります。
症状が出ている葉っぱは取り除き、薬剤を散布して治療しましょう。
枝枯病(キャンカー)
|
症状 |
枝に斑点が出てカサカサになり、枝が枯れます。 |
|
原因 |
雨水や虫を介して、剪定時の切り口や傷んだ枝から病原菌が侵入して感染します。 |
|
発生しやすい時期 |
通年で発生する可能性がある病気です。 |
|
対処法 |
症状が出ている枝を取り除き、切り口に薬剤を塗布します。 |
枝枯病(キャンカー)は、枝に紫褐色の斑点が出る病気です。やがて、枝全体に広がって枝葉が枯れてしまいます。
雨水や虫によって運ばれた病原菌が剪定時の切り口や傷んだ枝から侵入して感染し、年数の経ったバラに起きやすい病気です。
枝枯病と見られる症状が出ている枝は取り除き、切り口に薬剤を塗って治療しましょう。
根頭がん腫病
|
症状 |
根や株もとにこぶ状のふくらみができ、生育を阻害します。 |
|
原因 |
根などの傷から病原菌が侵入して感染します。 |
|
発生しやすい時期 |
通年で発生する可能性がある病気です。 |
|
対処法 |
ふくらみを切除し、切り口に薬剤を塗ります。 |
根頭がん腫病は、バラの根や株もとにこぶのようなものができる病気です。最初は白いこぶが少しずつ黒っぽい色に変化し、ガサガサした泡が固まったような膨れ方をします。
弱い株でなければ、枯れるほどの被害はありませんが、ほかと比べて生育が悪くなります。
原因は根などの傷から侵入した菌です。発生した際はふくらんだこぶを除去し、切り口に薬剤を塗って治療します。
バラの病気を治療する方法
バラが病気にかかった場合、感染が広がる前の早期治療が大切です。
症状の出ている葉っぱや花などは速やかに取り除いて、有効な薬剤を散布しましょう。落ちた葉っぱや花にも病原菌が残っているため放置せず、薬剤散布前に拾って処分してください。
バラの病気予防・治療には「ベニカXネクストスプレー」
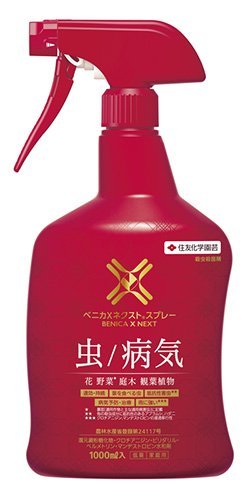
「ベニカXネクストスプレー」は、うどんこ病や黒星病に有効なスプレータイプの殺虫殺菌剤です。バラを食い荒らす害虫退治だけでなく、殺菌成分が病気の予防・治療にも効果を発揮します。
雨にも強く、長雨シーズンの病気予防に効果的です。手が疲れにくい形状をしているため、散布作業も楽にできるでしょう。
「マイローズ殺菌スプレー」も併用してローテーション散布

「マイローズ殺菌スプレー」も、バラがかかりやすいうどんこ病や黒星病に有効なスプレータイプの殺虫殺菌剤です。無色透明な液体で、散布後の葉汚れが少ないのが特徴です。
病気の予防や治療に使う薬剤は、同じものを使い続けると効果が出にくくなります。ベニカXネクストスプレーと併せて、複数の薬剤を使ったローテーション散布がおすすめです。
バラの病気を予防する方法
病気の早期発見と治療は重要ですが、そもそもバラが病気にかからない環境を整え、丈夫に育てることも大切です。
蒸れやすい環境だと繁殖力が強くなる病原菌が多いため、定期的にバラの枝葉を剪定し、風通しの良い状態にしましょう。土のなかに潜む病原菌への対策には、跳ね返りに注意して水やりし、鉢植えなら雨の日は場所を変えるなど工夫します。
また、成長に必要な栄養を適切に与え、丈夫で抵抗力の高いバラを育てましょう。
抵抗力を高めて病気を予防する「ベニカXガード粒剤」
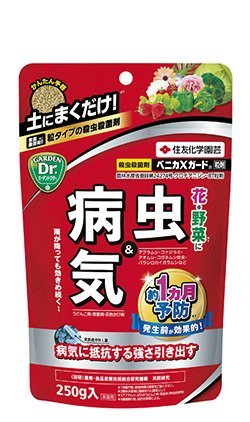
「ベニカXガード粒剤」は、土に混ぜ込む、またはまくだけで効果を発揮する殺虫殺菌粒剤です。
微生物の作用で植物の抵抗力を高め、うどんこ病、黒星病、灰色かび病の予防に効果を発揮します。また、根から殺虫成分が吸収されてバラの葉っぱに行き渡るため、病気を呼び込む害虫対策にも有効です。
丈夫に育てる「マイローズばらの天然有機肥料」

「マイローズばらの天然有機肥料」は、動物質有機肥料を配合した肥料です。植え付け時の元肥にも、植えてから与える追肥にも使え、継続的に利用すれば土壌内の有用微生物を活性化します。
バラがしっかり根を張れる土壌環境を整えれば丈夫に育ち、美しい花を楽しめます。
まとめ
バラの代表的な病気は、うどんこ病や黒星病のほか、さび病、灰色かび病、ベト病、枝枯病、根頭がん腫病などです。いずれも症状が出ている部分を取り除き、薬剤を散布して治療します。
バラの病気治療には、ベニカXネクストスプレーやマイローズ殺菌スプレーがおすすめです。
また、バラの生育に適した肥料や薬剤を使った病気の予防も大切です。ベニカXガード粒剤やマイローズばらの天然有機肥料を使い、健康で抵抗力の高いバラを育てましょう。



