目次
知っておきたい園芸情報 - 園芸コラム樹木につく害虫とは?種類や発生しやすい時期、効果的な対策方法

自宅の庭をきれいに保ちたいけれど、樹木や花木に害虫がつき、葉が食べられたり花を枯らされたりしてしまうと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
アブラムシやハダニなどの害虫を放置すると、樹木が深刻な被害を受ける場合があり、適切な対策を行うことが大切です。
この記事では、樹木につく害虫のおもな種類や発生しやすい時期、効果的な対策方法について解説します。併せて、おすすめの薬剤も紹介するため、美しく健康な庭づくりの参考にしてください。
樹木につく害虫対策の重要性
庭の美観にかかわる樹木には、アブラムシやカイガラムシ、ハダニなど、さまざまな害虫がつきます。
樹木についた害虫を放置すると、害虫に栄養を奪われて樹木が弱り、病気にかかりやすくなってしまいます。最悪の場合には、樹木が枯死してしまうでしょう。
しかし、適切に害虫対策を行えば、このような被害を最小限に抑えられる可能性があります。樹木の美しさと健康を維持して庭の美観を保つためには、害虫対策を行うことが重要です。
樹木につくことの多い7種類の害虫
樹木につく害虫といっても、その種類は多種多様です。そのため、それぞれの害虫が持つ特徴や樹木に与える影響は異なります。
ここでは、樹木につくことの多い害虫を7種類紹介します。
1.アブラムシ

アブラムシは、樹木の新芽や葉裏に寄生し、植物の汁液を吸収して生きる小さな害虫です。被害を受けた樹木は芽が縮れるほか、葉にコブなどができます。これにより、樹木の美観が損なわれるだけでなく、生育が阻害されることがあります。
アブラムシは「甘露」と呼ばれる粘着性のある排せつ物を出し、これがすす病の原因となることも少なくありません。すす病とは、植物に付着した甘露にカビが繁殖して葉や幹を黒く覆う現象のことです。この現象が起きると樹木の美観を損ない、深刻な場合には葉の機能低下(光合成阻害や葉の表面からの蒸散を妨げる)を招きます。
また、アブラムシはウイルス病にかかった植物の汁液を吸うことでウイルスを体内に取り込み、他の植物へ移動して汁液することで、「モザイク病」と呼ばれるウイルス病を媒介します。葉の黄化や生育不良など、樹木にさらなる被害をおよぼす可能性もあるでしょう。
2.ハダニ

ハダニは葉の裏側に寄生する害虫で、肉眼での発見が難しいほど微小な生物です。高温や乾燥した環境を好むため、梅雨明けから9月頃にかけて繁殖が盛んになります。
ハダニは、口針で葉を刺して汁液を吸い取る習性があります。吸い取られた部分の葉緑素が抜けて、葉の表面に白い小さな斑点が現れたように見え、葉の裏側は褐変します。それによって被害に気付くことが少なくないでしょう。被害が進行すると葉の色が悪くなるだけでなく、樹木の生育にも影響します。
また、ハダニはクモのように細い糸を出し、この糸を利用しつつ風に乗って移動するため、花にも被害がおよぶことがあります。ハダニは繁殖力が強く、防除が遅れると急速に増える可能性があることから、早期発見と迅速な対策が必要です。
3.カミキリムシ

カミキリムシは幼虫・成虫ともに木を食べる害虫ですが、特に注意したいのが幼虫による食害です。
「テッポウムシ」とも呼ばれるカミキリムシの幼虫は樹木の内部に潜り込み、1~2年にわたって幹の内側を食べ進めます。幹に穴を開けることで樹木に大きなダメージを与え、樹木を弱らせてしまいます。
一方、成虫のカミキリムシは若い枝を好んで食べます。かじられた枝は枯れてしまうこともあるため、こちらも注意が必要です。
4.ケムシ

ケムシはガやチョウの幼虫の俗称で、おもに樹木の葉を食害します。ケムシの食欲は旺盛で、被害が広範囲にわたることも少なくありません。
また、一部の種類のケムシは毒毛を持っています。毒毛は抜けやすく、人がうっかりケムシに触れると、簡単に人の手などに付着します。毒毛が刺さると、かゆみやかぶれなどを引き起こすことがあるため、注意が必要です。
このように、人にも被害がおよぶおそれがあるため、ケムシの駆除は重要といえます。
5.グンバイムシ

グンバイムシは、翅(はね)をたたむと軍配のような平たい形をしているのが特徴的な害虫です。
葉の裏側に寄生し、植物の汁液を吸う習性があります。これによって葉緑素が抜けると、葉の表側に白く小さな斑点が現れたようになり、美観を損ねてしまいます。被害が進行すると葉が全体的に白っぽくなり、落葉を引き起こすこともあります。
グンバイムシは4月頃から活動し始めますが、高温や乾燥した環境を好み、特に夏になると大量発生します。大量発生すると被害が樹木全体に広がり、樹木が衰弱してしまう可能性もあるでしょう。
6.ナメクジ

ナメクジは、湿った環境を好む夜行性の食害性害虫です。植物の柔らかい部分を好み、若い葉や新芽、花弁を食べることで樹木に被害を与え、被害を受けた箇所には穴が開いてしまいます。新芽が食べられた場合には、葉の生育にも影響することがあります。
また、ナメクジが這った跡には特有の粘液が残るため、不快害虫として扱われることもあります。
7.カイガラムシ

カイガラムシは種類が多く、日本国内だけでも400種類以上が確認されています。その多くが貝殻のような殻をかぶっている特徴的な害虫です。
カイガラムシは樹木の幹や枝に寄生して汁液を吸収します。寄生された樹木は、美観を損なうだけでなく、汁液を吸われることで生育にも影響が出てしまいます。
また、カイガラムシは間接的な被害をもたらす可能性があることにも、注意が必要です。具体的には、糖分を多く含む白くベタベタとした排せつ物が原因で、すす病を引き起こすことがあります。
この現象が起きると樹木の美観を損ない、深刻な場合には葉の機能低下(光合成阻害や葉の表面からの蒸散を妨げる)を招きます。
《樹木別》つきやすいおもな害虫

樹木の種類によって、つきやすい害虫は異なります。下表では、庭木として植えられることの多い樹木と、それらにつきやすいおもな害虫を紹介します。
|
樹木 |
つきやすいおもな害虫 |
|
シラカシ |
アブラムシ、ケムシ、カイガラムシなど |
|
ウバメガシ |
アブラムシ、ケムシ、カイガラムシなど |
|
ハナミズキ |
アブラムシ、ケムシ、カイガラムシなど |
|
キンモクセイ |
アブラムシ、ケムシ、カイガラムシなど |
|
レッドロビン |
アブラムシ、カミキリムシ(幼虫)など |
|
ドウダンツツジ |
ハダニ、カミキリムシなど |
|
シマトネリコ |
ケムシ、カイガラムシなど |
これらの害虫は、それぞれ樹木に被害を与える可能性があるため、後述する方法で対策しましょう。
樹木につく害虫が発生しやすい時期は?
樹木につく害虫は、発生しやすい時期がそれぞれ異なります。下表は、おもな害虫とその発生時期をまとめたものです。
|
害虫 |
発生しやすい時期 |
|
アブラムシ |
4~6月、9月~10月 |
|
ハダニ |
4~10月(梅雨期を除く) |
|
カミキリムシ(成虫) |
5月~9月 |
|
カミキリムシ(幼虫) |
1年中 |
|
ケムシ |
5月~6月、8~10月 |
|
グンバイムシ |
5月~9月 |
|
ナメクジ |
5月~6月、9月~10月 |
|
カイガラムシ |
5月~10月 |
この表を参考に、季節ごとに注意すべき害虫を把握し、適切な時期に予防や対策を行いましょう。
樹木につく害虫への効果的な対策方法

樹木の健康を守るためには、害虫対策が欠かせません。ここでは、樹木につく害虫への効果的な対策方法を3つ紹介します。
日当たりや風通しを良くする
害虫は、基本的に日当たりの悪い場所や風通しの悪い環境下で発生しやすくなります。
このような環境にしないためには、定期的に剪定を行い、樹木の枝葉が密集しないようにすることが大切です。これにより、日光が樹木全体に行きわたり、風通しも良くなります。
また、除草をこまめに行うことも重要です。樹木の周囲に草が密生していると、害虫の隠れ家になりやすく、発生を助長する可能性があります。樹木の周辺をきれいに保つことで、害虫の住処を減らせるでしょう。
定期的に観察する
害虫対策では早期発見が重要です。定期的に樹木を観察することで、被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。
特に、葉の裏側や樹木下部の幹に注意しましょう。害虫は葉の裏側に潜んでいる場合もあるため、注意深くチェックすることが大切です。
観察の際は、葉の変色や変形、枝の異変、糞、幼虫が削ったおが屑などの有無もしっかりと確認しましょう。ささいな変化でも見逃さないよう、定期的かつ丁寧な観察を行うことが重要です。
薬剤で駆除する
害虫は、薬剤による駆除が効果的です。薬剤を使用した害虫駆除は比較的簡単で、初心者でも手軽に行うことができるでしょう。忙しい方でも、手間をかけずに効果的な対策ができます。
薬剤を使用する際は、ラベルに記載された指示に必ず従い、適切な時期と方法で散布することが重要です。使用量や散布回数、使用上の注意事項などをしっかりと確認し、適切に使用してください。
樹木につく害虫の駆除におすすめの薬剤3選
樹木の害虫対策には、適切な薬剤を選ぶことが大切です。ここでは、特におすすめの薬剤を3つ紹介します。
さまざまな害虫に効果がある「ベニカXネクストスプレー」

「ベニカXネクストスプレー」は、害虫に素早く効き、長期間にわたって効果を発揮します。例えば、アブラムシの場合、約1ヵ月の効果持続が期待できます。
ベニカXネクストスプレーの強みは、通常退治が難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)や薬剤抵抗性を持つ害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効果を発揮する点です。さまざまな害虫に効果がある薬剤といえるでしょう。
【適用害虫】ハダニ類、アブラムシ類、アザミウマ類など
樹幹に食入する幼虫を効果的に退治する「園芸用キンチョールE」
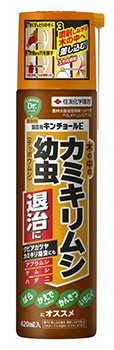
「園芸用キンチョールE」の特徴は、3方向噴射が可能な専用ノズルにあります。樹幹に食入する幼虫を効果的に退治できるため、カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)対策に特におすすめです。
隠れた幼虫にも効果的に作用し、害虫の被害を最小限に抑えることが期待できるでしょう。
【適用害虫】カミキリムシ、アブラムシ類、ケムシ類など
いろいろなケムシ退治に効果がある「ベニカケムシエアゾール」
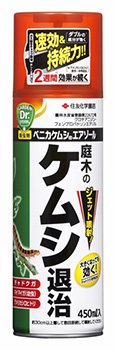
「ベニカケムシエアゾール」は、さまざまな庭木のケムシ退治に使用できる薬剤です。
速効性がありつつも、アメリカシロヒトリの若令~中令幼虫に対しては約2週間の持続効果があります。散布後に新たに発生した害虫も退治できるため、長く樹木を保護することができます。
【適用害虫】ケムシ類、アブラムシ類、ミノウスバ、ツツジグンバイなど
まとめ
樹木につく害虫は、庭の樹木に深刻な被害をもたらします。害虫の種類や発生時期を理解し、適切な対策を行うことが大切です。
具体的な対策方法としては、まず害虫の発生リスクを減らすために、日当たりや風通しを良くします。そして、定期的な観察で早期発見を心がけ、害虫を確認した場合は速やかに薬剤を使用して駆除します。
これらのポイントを押さえて大切な樹木を守り、美しく健康な庭を維持しましょう。



