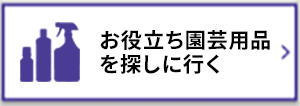1.園芸作業をはじめる前に
1-3.樹木(植木)とは
植物の茎の中には維管束という水分や養分の通り道があり、主として水の通路になる木部(道管部)がよく発達してかたく丈夫な茎をもつ植物を木本といい、開花・結実を繰り返しながら何年も生き続け、茎が太くなって幹や枝になっていくものです。 庭などに植えられる観賞用樹木の分類も、植物学とは違った分け方をします。落葉樹や常緑樹などの性質で、あるいは、高さや日当たりを好むか、日陰に耐えられるかどうか、さらに、樹形などによっても分類されています。
樹木の分類
■性質によって分ける
樹木を性質で分類すると、年間を通して緑を保つ常緑のグループと、休眠期に葉を落とすグループに分かれる。
・常緑樹
一年中葉がついている木のことだが、常緑とはいえ、ずっと葉が落ちないわけではない。古い葉が落ちる前に新しい葉が出て、新旧交代しているが、一斉に落ちることはない。マツ類、スギ、ヒノキなどの針葉樹とツバキ、サザンカ、シラカシなどの広葉樹がある。

・落葉樹
冬の低温期や乾燥期の生育に適さないときに葉を落として休眠し、生育期になると新しい葉が出てくる木。一般的に夏に葉を茂らせ、秋から冬に落葉。多くの花木がこれに属し、秋の紅葉が美しいものもある。カラマツ、メタセコイヤなどの針葉樹とナツツバキ、ハナミズキ、モクレン、サクラ、ケヤキ、クヌギ、イロハモミジなどの広葉樹がある。


■高さで分ける
成木になったときの木の高さで分けるが、日本の庭で庭木として植えた場合、本来の大きさとは異なることが多い。
基準の高さにはっきりした定義はないが、高木は8m以上、低木は3m以下、その中間を小高木、1m以下のものを小低木と呼ぶことが多い。
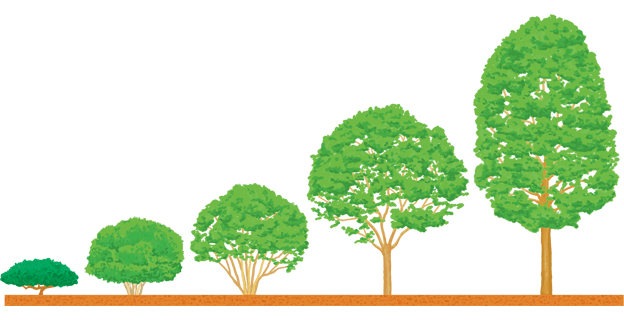
陽樹と陰樹
日当たりを好むか、あるいは日陰に耐えられるかどうかで分けることもあります。
クロマツ、アカマツ、シラカバ、オリーブなど日当たりが良い明るい場所を好む樹木を「陽樹」といい、あまり日の当たらない場所でも生育できる性質をもつアオキ、ヤツデ、カクレミノなどを「陰樹」といいます。陽樹は陰地では生育できませんが、陰樹は日陰に耐えて生育するという意味で、耐陰樹とも呼ばれています。アセビ、クチナシ、アジサイ、ジンチョウゲ、シャリンバイ、サンゴジュなどは日向でも生育できる陰樹です。