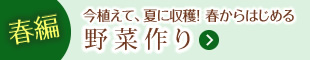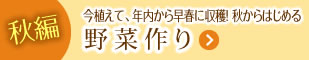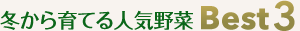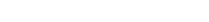秋に植えつけた大切な苗が心配ですが、寒さにあうからこそ生長のスイッチが入る不思議な野菜たち。
冬は、春を待つ楽しみとともに植物の生命力を間近で感じられる貴重な季節でもあります。

駆け抜けていく、年末年始の慌ただしさ。
そしていよいよ、1年でもっとも寒い時期がやってきます。
そんななかでも野菜は、ゆっくりじっくり生長しているので、日々の管理を怠らないようにしましょう。
タマネギの冬越し
ポリマルチをしなかった苗には、株元を敷き藁などで覆っておくと、霜で株が浮き上がるのを防げます。
植えつけた苗が細かった場合は、寒さに遭って傷んでしまうことがあります。また、植えつけに適する太さだった苗でも、しっかり根が張っていなかったりすると、霜で株が浮き上がり、根が乾いて枯れてしまうこともあります。敷き藁やバーク堆肥などを株元へ敷き込んで、霜で根が浮き上がるのを防ぎましょう。
菜園に植えたタマネギには、冬じゅう、水やりの必要はありませんが、天候や環境によって、苗がしおれるほど極端に乾きすぎる場合は、水やりをします。水やりは、暖かい日の午前中に行ないましょう。冷え込む日に水やりをすると降霜を助長しますので、控えるようにします。
タマネギの子球を植えて、コンテナ栽培をしている場合は、収穫適期を過ぎてしまいます。早めに抜き取って、収穫を終えてしまいましょう。
エンドウの冬越し
寒風が強く吹きつけると、エンドウは葉やつるが傷んでしまいます。強い風で風除けが倒伏しないように、注意してください。
菜園に植えたエンドウには、基本的に水やりは不要です。しかし、天候や環境によって、極端に乾きすぎる場合は、暖かい日の午前中に水を与えましょう。
株元には敷きわらやバーク堆肥などを敷き込み、霜で株が持ち上がって根が乾いてしまうのを防ぎます。
先月に引き続き、寒風に当てないように、寒風除けは忘れず設置しましょう。多少の雪も防ぐことができます。なお、寒風避けのよしずなどが、強風で倒れ込んで、株を折ったりしないように注意が必要です。
プランターで栽培しているエンドウは、用土が乾いたらたっぷり水やりをしましょう。先月と引き続き、置き場所は南向きの軒下などを選び、寒風に当てないように管理することが大切です。
イチゴの管理
イチゴは極端な寒風にさらさないようにしつつ、ある程度の寒さに当てて冬越しをさせないと、花芽ができません。
|
|
| 注:写真は1月の生育状況とはことなります。 |
|
まだ株元に敷きわらを施していない株には、できるだけ敷いておきましょう。極端に強い寒風に当たると傷むことはありますが、寒さに当てないと花芽ができないので、敷きわら程度の防寒で冬越しさせます。
積雪がある地方では、雪に埋めてしまったほうが、寒風などが当たらないうえに、湿度も保てます。
プランターで栽培しているイチゴは、南向きの軒下など、寒風を避けられる戸外に置き、表土が乾いたら水やりをして管理を続けます。同じく積雪がある地方では、思い切ってプランターをすっぽり雪に埋めてしまっても大丈夫です。 いずれも枯れ葉が目についたら、つけ根から切っておきましょう。
 病害虫ナビを見る
病害虫ナビを見る
 ・
・
タマネギ、エンドウ、イチゴともに、この時期に目立つ害虫や病気は特にありません。

1年でもっとも寒い時期だから、野菜の成長は一時的に止まっていたり、ごくごくゆっくりだったりしますが、引き続き寒風に当てないようにしましょう。2月下旬ごろから、春に向かって成長が始まります。
タマネギの冬越し・2
霜で株が浮き上がらないように、株元にはしっかり土を寄せておきましょう。プランター栽培でも同様に土寄せします。
寒さや霜で傷まないように、株元への土寄せはしっかりと行います。
菜園では、葉がしおれるほど乾きすぎなければ、水やりは不要です。プランター栽培では乾かし気味に管理しますが、同様に葉がしおれるようなら水やりをします。
2月下旬になったら株元へ、粒状肥料「マイガーデンベジフル」を1m²当たり120g施します。
プランター栽培の場合は、用土1ℓ当たり4gを目安に施しましょう。
エンドウの冬越し・2
敷きわらやバーク堆肥などでマルチングして、霜で株が持ち上がるのを防ぎましょう。
菜園、プランターともにしおれるほど乾きすぎるときは、暖かい日の午前中に水を与えましょう。
できるだけ寒風に当てないようにしたいので、移動できるプランター栽培の場合は、北風の当たらない南向きの軒下などに置きます。
2月下旬ごろになると、つるあり種では、そろそろつるが伸びてくる株があります。支柱やネットを設置して、絡ませましょう。
イチゴの管理・2
黒いマルチフィルムを株の上からかぶせて、株のところをカッターで切ってマルチングをします。
2〜3月になったらマルチフィルムを張っていない株には、上から黒いマルチフィルムをかぶせ、手で株の位置を確かめながらカッターで切り込みを入れて株をのぞかせ、マルチングをしましょう。泥で葉や果実が汚れたり病気が発生するのを防ぎます。また、黒いマルチフィルムなら、地温を上げるのにも役立ちます。
プランター植えの株は、極端に乾かしすぎないように水やりをします。
赤くなった葉は病気ではなく、寒さによる紅葉です。枯れてきたらつけ根でカットして取り除きましょう。ほか、傷んだ葉も摘み取っておきます。
 病害虫ナビを見る
病害虫ナビを見る
 ・
・
タマネギ、エンドウ、イチゴともに、この時期に目立つ害虫や病気は特にありません。
コラム/天地返し
1年で一番寒い時期だからできる作業があります。それは「天地返し」です。菜園の土は表土に近いほど、野菜に吸収されなかった肥料分が残っていたり、土が硬くなったりしています。逆に土中には、害虫の卵や幼虫が潜んでいることがあります。土を掘り返し、表面の土と土中深い位置にある土と入れ替えることを「天地返し」と呼んでいます。
まず、深さ30cmほどの土を掘り上げ、さらに30cmほど掘り上げます。最初に掘り上げた分の土を、先に穴に埋め戻し、土中深い位置にあった土を、その上に重ねて戻します。
土を掘り上げたときに1週間ほど地表で晒すと、より効果的です。 プランター栽培派なら、ポリシートなどを広げたところに、使用後の鉢土をざっと薄く広げ、1ヶ月ほど干すとよいでしょう。古土を再利用するときは、古い根の残がいなどを処分してからみじんをふるい分け、2倍量以上の新しい土を加えてから使用します。

寒さが緩み、春の兆しに心が躍る3月を迎えます。冬の間、じっと寒さに耐えていた野菜たちも、気づけば目を覚まし、成長を始めています。ただし、霜と低温には、もうしばらく注意が必要です。
タマネギの追肥
2月下旬になったら粒状肥料を追肥し、さらに3月下旬には、液体肥料も施しましょう。

タマネギの生育が旺盛になる時期です。2月下旬になったら株元へ、粒状肥料「マイガーデンベジフル」を1m2当たり200g施します。
さらに、3月下旬になったら、液体肥料「ベジフル液肥」の1000倍液を、追肥として1週間に1〜2回、株元へ施しましょう。
また、乾燥を防ぐために、引き続き株元への土寄せはしっかりと行います。
なお、プランター栽培の場合は、萎れないように乾いたら水やりを行います。また、追肥は、用土1ℓ当たり「マイガーデンベジフル」7gを目安に施します。
そのまま管理を続け、5〜6月に葉が倒れたら収穫のタイミングです。晴天が続き、土が乾いているときに収穫するとよいでしょう。
エンドウの追肥と誘引
つるあり種はこまめに誘引し、強風などで倒れないよう、支柱をしっかり立てましょう。液体肥料の追肥も開始します。
液体肥料「ベジフル液肥」の500倍液を、追肥として1週間に1回、株元へ施しましょう。
強風などで倒れないように、株元にはしっかり土寄せをし、支柱が倒れないように注意します。つるあり種のつるは、こまめに誘引しておきます。
4月になると、そろそろ収穫ができます。サヤエンドウはさやの中の実が確認できるようになったら、スナップエンドウはさやがふっくらと膨らんだら収穫できます。6月ぐらいまで、順次収穫しましょう。
イチゴの追肥
果実を肥大させるために、粒状肥料と液体肥料で、しっかり追肥を行います。プランター栽培では、水ぎれさせないように注意します。
3月に入ったらすぐ、株元に粒状肥料「マイガーデンベジフル」1m²当たり150gを株元に追肥します。同時に株元の土を、軽くほぐしておくとよいでしょう。さらに、液体肥料「ベジフル液肥」の500倍液を、1週間に1〜2回施します。
気温が上がってくるので、特にプランター植えでは、水ぎれさせないように注意します。
果実が肥大し、緑、白、赤と色づいてきます。5〜6月にへたのつけ根部分まで赤くなったら収穫しましょう。なお、収穫期は「ナメクジ」の食害がふえるので、注意します。
 病害虫ナビを見る
病害虫ナビを見る
- 「ネギコガ」・「ハスモンヨトウ」(タマネギ)
- ネギコガはコナガに似た小さい蛾の幼虫で、暖かくなると発生して、タマネギをはじめとするネギ類の葉を内側から食害します。
「ハスモンヨトウ」は「ヨトウムシ」の仲間で、春と秋に発生し、葉を旺盛に食べて野菜に大きな被害を与えます。夜間活動する夜行性害虫なので昼間は見つけづらく、退治が厄介です。
いずれもタマネギの場合の防除には殺虫剤「ベニカS乳剤」を300倍で収穫7日前までに散布して防除します(散布は5回まで)。

ワタアブラムシ
(イチゴ)

ナモグリバエ成虫
(エンドウ)

ナモグリバエ被害
(エンドウ)
- 「灰色腐敗病」・「灰色かび病」(タマネギ)
- 「灰色かび病」は、湿度を好み、春先から梅雨前までに多く発生するかび性の病気です。
灰色腐敗病も、下葉からカビが発生して、ひどくなると枯死します。感染すると貯蔵中にもカビが拡がり、伝染します。
いずれもタマネギの防除には殺菌剤「GFベンレート水和剤」を2000倍で収穫前日までに散布します(散布は6回まで)。

うどんこ病(イチゴ)
コラム
2月には、菜園の土をリフレッシュさせる「天地返し」をご紹介しました。ここへ苦土石灰を1㎡当たり150g施して土をよく耕し、1週間後に堆肥を1m²当たり2kg、粒状肥料「マイガーデンベジフル」を1㎡当たり120g施してまんべんなく混ぜ込みます。これで下準備はOKです。
さらに、苗の植えつけ時やタネまき時に、土の殺菌・消毒用の病気予防になる殺菌剤「石原フロンサイド粉剤」を散布しておくと、根こぶ病・そうか病・「白絹病」・「苗立枯病」対策に役立ちます。
同じく殺虫剤では、「家庭園芸用サンケイダイアジノン粒剤3」を散布すると、植物の根を食害したり土の中に潜む「コガネムシ幼虫」・ウリハムシ幼虫・ケラ・「コオロギ」・タネバエなどの害虫退治に役立ちます。