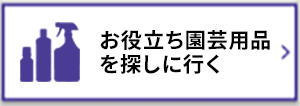暮らしの中で園芸を楽しむ園芸の基本
まずは知りたい園芸知識
ふやして楽しむテクニック:木や草花のリフレッシュと繁殖をご紹介します。このページではタネからふやすについてご紹介しています。
6.ふやして楽しむテクニック:木や草花のリフレッシュと繁殖
6-7.タネからふやす
植物からとったタネでふやすことを種子繁殖といいます。ふつう草花を育てるとき、花がらを摘んで手入れをしますが、花が終わるころに少しタネをつけておけば、それをまいて翌年も育てられます。ただし、F1品種は親と同じ花が咲かないので、同じものを育てたいなら、毎年タネを購入しましょう。
タネの採取
タネの採取はタイミングが大事です。実が熟すまで待っていると鳥に食べられたり、飛散したりして、よい種子が得られません。一般に、草花は全草が枯れてきたら、庭木や花木は実が色づき成熟するのを待って採取します。
ヒマワリの採種
作業適期 花後
① 9月の終わりごろ、花が下を向いたら切り取る。

② 風通しのよい軒下などに吊るし、7~10日ほど乾燥させる。

③ よく乾いたらタネをほぐす。

④ 密閉できるビニール袋に入れる。袋には花の名前や採種した日付などを書き、缶などに入れて保管する。

小さなタネをつける植物は、枯れた茎ごと刈り取り、タネがこぼれないように紙袋に入れて風通しのよい日陰で5~7日ほど乾燥させる。

急ぐときや天気が悪いときは、乾燥剤(シリカゲル)を入れた瓶の中で乾かす。

タネの保管方法
タネの発芽には水分と適当な温度が必要ですが、乾燥状態のときは活動を停止しているので、一般の草花の種子は、乾燥状態で密閉して、低温に置くと発芽力を保存できます。自分で採ったタネや余ったタネを貯蔵したいときは、十分に乾かした後、ビンや缶などの容器に入れて密封し、冷蔵庫に入れておきます。ただし、タネには寿命があるので、できるだけ次のまきどきにまくようにしましょう。発芽能力が衰えていることもあるので、少し多めにまきます。
まき残したタネは、再び絵袋に入れ、乾燥剤とともにビンや缶などに入れて密閉し、冷蔵庫の野菜ボックスに入れておく。絵袋には購入した年月日、タネをまいた年月日を記入しておく

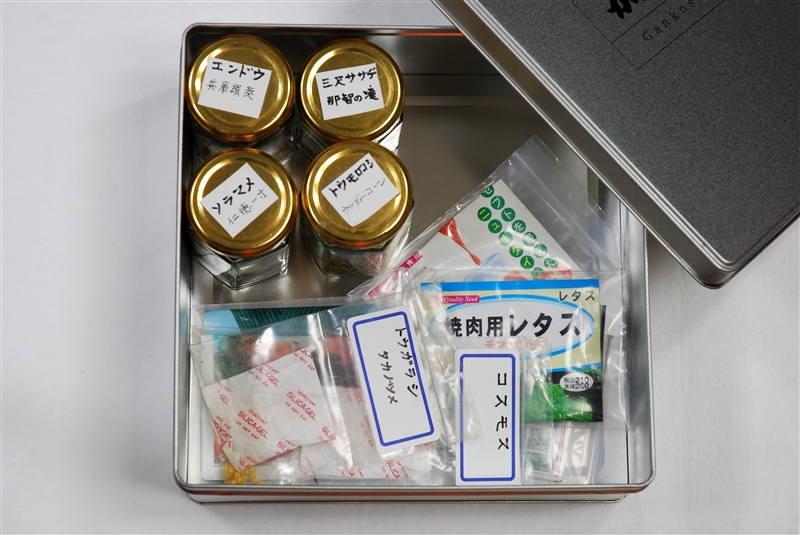

タネの寿命
タネにも寿命があります。一般的には2~3年です。ホウセンカやアサガオのように5年程度、ワスレナグサやトレニアは1年程度など、植物によって発芽能力の持続期間が大よそ決まっています。ただし、寿命の長いタネでも保存状態が悪ければ、発芽率は悪くなります。乾燥させた状態で、温度を低く保って上手に保存しましょう。
アスター(キク科)


寿命が1~2年と短いものを短命種子という。アスターは寿命が1年の短命種子。
ジニア(キク科)


寿命が2~3年のものを常命種子という。ジニアの寿命は2~3年。
ケイトウ(ヒユ科)
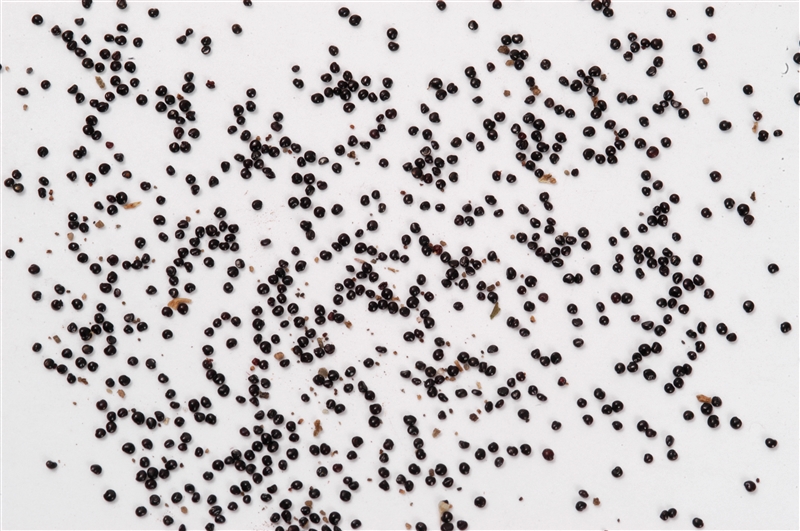

寿命が5~6年以上のものを長命種子という。ケイトウの寿命は5~6年。
草花・野菜のタネの寿命
【草花のタネの寿命】
・1年程度
カルセオラリア、トレニア、スイートアリッサム、フロックス・ドラモンディー、ワスレナグサ、球根ベゴニア、ハルシャギク、ジギタリス、ニチニチソウ、サルビア、ローダンセなど
・1~2年程度
コスモス、カイザイク、クラーキア、キキョウ、インパチェンス、エゾギクなど
・2年程度
タチアオイ、ヒナギク、ダリア、ハナビシソウ、フレンチ・マリーゴールド、センニチコウ、アゲラタム、リナリア、ロベリア、パンジー、バーベナ、マツバボタン、ハナビシソウ、カスミソウ、クロタネソウ、オジギソウ、オニゲシ、マツムシソウ、シネラリアなど
・2~3年程度
キンセンカ、カーネーション、セキチク、ペチュニア、ムシトリナデシコ、ジニア、スイートピーなど
・3年程度
キンギョソウ、ブラキカム、ルコウソウ、ルピナス、シザンサス、ストック、シクラメン、ヤグルマギクなど
・4年程度
ヘリアンサス、マリーゴールドなど
・5~6年程度
ハゲイトウ、ケイトウ、スイセンノウ、ホウセンカ、アグロステンマ、アサガオなど
【野菜のタネの寿命】
寿命が1年と短い短命種子
シソ(シソ科)


寿命が2年の常命種子
キャベツ(アブラナ科)


寿命が4~6年と長い長命種子
ナス(ナス科)


・1年程度
シソ、ミツバ、ネギ、ニラ、タマネギ、ニンジン、ラッカセイなど
・2年程度
キャベツ、レタス、トウガラシ、ホウレンソウ、ゴボウ、エンドウ、インゲンなど
・3年程度
ダイコン、カブ、ハクサイ、漬け菜類、キュウリ、カボチャなど
・4年以上
ナス、トマト、スイカ、オクラ、ソラマメ、アズキなど