目次
知っておきたい園芸情報 - 園芸コラム地植えのバラが枯れる原因とは?枯らさないように育てる方法を紹介

「美しいバラが咲く素敵なお庭を作りたい」と思うものの、バラを育てるのが初めてだと、うまく育てられるか不安になってしまうかもしれません。また、実際に地植えでバラを育ててみたものの、思ったように生育せず枯れてしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。
基本的にバラは強い植物ですが、何らかの原因によって枯れてしまう場合もあります。
本記事では、地植えでバラを育てる際にバラが枯れてしまう原因や、枯らさずに育てる方法を解説していきます。
地植えのバラが枯れる原因
地植えのバラは、病気や害虫が原因で枯れることがあります。
バラがかかりやすい病気としては、黒星病(黒点病)やうどんこ病、根頭がんしゅ病などが挙げられます。バラに付きやすい害虫は、ハダニやアブラムシ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、カミキリムシ、コガネムシなどです。
また、バラは根が完全に乾くと枯れてしまうため、乾燥にも注意しましょう。夏場の強い日光に当たると、葉が日焼けしてしまうこともあります。
近年では温暖化の影響で、冬になっても栄養を蓄えるための休眠が十分にできず、その結果バラが思うように育たないこともあります。逆に、寒い冬に土の中の水分が凍ったり解けたりを繰り返した結果、根が腐ってしまうこともあります。
特に、植えたばかりでまだ根がしっかり張っていないバラは枯れやすいとされているため、注意が必要です。
バラがかかりやすい病気と対処方法

ここからは、地植えのバラがかかりやすい3つの病気とその対処方法を紹介します。
黒星病(黒点病)

黒星病(黒点病)は、バラの葉の表面に黒い斑点ができる病気のことです。黒星病にかかった葉は変色して落ち、そのままにしておくと株そのものが枯れてしまうことがあります。
黒星病の原因は、土の中に含まれている糸状菌(カビ)です。雨や水やりで土に触れた水が細菌を含み、跳ね返ってバラの葉などに付着することで発生します。そのため、黒星病は雨の多い時期に発生することが少なくありません。
地植えでバラを育てるときは、なるべく雨にさらされにくい場所を選びましょう。水が跳ねないよう、優しく水やりをすることも大切です。
【黒星病(黒点病)にかかったときの対処方法】
感染が拡大しないよう、黒い斑点が付いた葉を取り除き、薬剤を散布してください。黒点が付き、落葉した枯れ葉はこまめに拾って、生ごみとして処分し発生源をなくします。枯れ葉を地面の上に放置しておくと、土中に菌が潜り込み、その後、何度も発生することになります。
肥培管理ではチッ素過多にならないよう、リン酸の多い肥料でバランスのとれた管理を心がけます。鉢植えの場合なるべく雨に当たらないようにしましょう。
うどんこ病

うどんこ病は、バラの葉や茎がうどんの粉のような白いものに覆われてしまう病気です。白い粉はカビの一種で、そのままにしておくと枯れる原因となります。
うどんこ病は、春や秋のように、昼と夜の温度差が大きい時期に多く発生します。風通しが悪くじめじめした場所で発生しやすいため、なるべく風通しの良い場所で栽培しましょう。
【うどんこ病にかかったときの対処方法】
黒星病と同じく、病気に感染した葉を取り除き、薬剤を散布してください。台所で使用する重曹を1000倍に希釈して散布しても、ある程度抑えることができます。
強アルカリ性溶液で、カビの菌糸を分断してやっつけます。肥培管理ではチッ素過多にならないよう、リン酸の多い肥料でバランスを意識した肥料やりを心がけましょう。
根頭がんしゅ病

根頭がんしゅ病は、バラの付け根近くの幹や根の部分にこぶのようなものができる病気です。土の中の病原菌が、茎や根に付いた傷口から侵入することで発生します。
根頭がんしゅ病の原因となる病原菌自体の感染力は、あまり高くありません。しかし、一度植物に潜伏すると増殖し、土を介してほかの株にも感染を広げてしまいます。使用したスコップや、靴の裏に付着した土から感染が広がることもあります。
【根頭がんしゅ病にかかったときの対処方法】
根頭がんしゅ病の完治を目指すのは非常に難しいため、基本的には株ごとすぐに処分することをおすすめします。根頭がんしゅ病にかかったバラが植えられていた土も廃棄し、使用したスコップやハサミ、靴の裏などを消毒するようにしましょう。
また、リゾビウムという病原細菌は14~30℃で生育します。春先の22℃あたりが生育適温なので、あっという間に広がっていきます。病原細菌は土壌伝染していき、傷口から侵入し、接触伝染によっても広がり、土壌中に長く生存しています。
発病株は全身が汚染されており、汚染株を切った刃物、掘り起こしたりしたスコップなどにも病原細菌が付着しているので、台所用漂白剤を10倍に希釈して浸漬殺菌するか、65℃以上、数時間の湯温処理を行って殺菌します。なお、病原細菌の死滅温度は51℃といわれています。
バラに付きやすい害虫と対処方法
ここからは、バラを育てる際に注意したい害虫の特徴と、その対処方法を紹介します。
ハダニ

ハダニはバラの葉の裏側に寄生し、養分や水分を吸って枯れさせたり、光合成を阻害して成長を妨げたりするやっかいな害虫です。初夏から夏に多く発生し、雨が当たりにくく乾燥しやすいベランダなどでほぼ年間を通して発生します。ハダニに吸われた箇所は白い斑点が生じたり、クモの巣に覆われたような状態になったりします。
ハダニが付きやすいのは、高温になる夏場です。体長0.5mm程度と小さいため、気付かないうちに被害が拡大してしまうことも少なくありません。特に夏場は、こまめに葉の裏側を確認しましょう。
【ハダニの対処方法】
葉の裏側をチェックしてハダニ被害に遭った葉を取り除き、残った葉には水をかけておきましょう。ホースやジョウロのハス口で、葉の裏側を中心に勢いよく葉水して防除します。水をかけることで、葉に付いたハダニを洗い流すことができます。
ハマナス系やオールドローズなど、葉のしわが深い品種が被害を受けやすいので、水をかけても取り除けない場合は、薬剤を使用してください。
アブラムシ

アブラムシは小さな虫で、バラの葉やつぼみから養分を吸い取ります。アブラムシの被害を受けた葉は元気がなくなり、成長しづらくなります。短期間で数が増えてしまうため、早めに対処するようにしましょう。
【アブラムシの対処方法】
数が少ない場合は手で取り除き、数が多くて取り切れない場合は葉を水で洗います。それでも取り除くのが難しければ、薬剤を使用しましょう。多くの薬剤で効果がありますが、効果が長く続く浸透移行性剤の使用がおすすめです。
アブラムシはキラキラした光を嫌うため、5cm四方のアルミホイルを紐で枝に吊り下げたりすることも効果的です。
バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)

バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)は、象の鼻のような長い口を持つ虫です。バラの新芽やつぼみに卵を産み、その部位を枯らしてしまいます。バラゾウムシの被害を受けた新芽やつぼみは、真っ黒に焦げたような状態になります。
【バラゾウムシの対処方法】
バラゾウムシは、危険を感じると地面に落ちる性質があります。バラゾウムシが付いているのを見つけたら、バラの枝を揺らして地面に落とし捕獲してください。すでに卵が産み付けられた部位は取り除きましょう。発生初期に新芽の先端を中心に薬剤散布します。
カミキリムシ

カミキリムシは細長い甲虫です。バラの株の根元近くに卵を産み、孵化した幼虫が茎の中に入りこんで食害します。カミキリムシの幼虫に寄生されたバラは中身が空洞になり、枯れてしまいます。
【カミキリムシの対処方法】
カミキリムシの成虫を見つけたら、すぐに捕獲して処分しましょう。幼虫の侵入を見逃さないように、株元の雑草を取り除きます。晩秋以降、すでにカミキリムシの幼虫が侵入してしまったバラは、株の根元に穴が開いており、そこから木くずのようなフンが出ています。
コガネムシ

乳白色で丸まっているコガネムシの幼虫は、土の中に生息し、バラの根を食べてしまうことがあります。一見病気ではなさそうなのにバラの元気がなくなっている場合は、コガネムシの幼虫が原因である可能性があります。
【コガネムシの対処方法】
成虫は見つけ次第捕殺します。周辺の土を耕して、コガネムシの幼虫を見つけたら駆除しましょう。毎年幼虫が出てくるようであれば、殺虫剤をあらかじめ土に混ぜておくことをおすすめします。
地植えのバラが枯れるのを防ぐポイント

ガーデニングでバラを育てるときには、地植えで育てる方法と鉢植えで育てる方法があります。どちらにもメリット・デメリットはありますが、地植えは鉢植えと比べると根が張って大きく育ちやすいのが特徴です。
今回は、地植えのバラを枯らさないように育てるポイントを紹介していきます。
初心者は大苗を選ぶ
バラの苗には、新苗と大苗があります。新苗は1年目の若い苗で、大苗は新苗を畑で1年間育てて大きくしたもののことです。
バラを育てるのが初めての方は、すでに大きく育っており比較的丈夫な大苗を購入することをおすすめします。
間隔を空けて植える
地植えのバラは、適切な環境で育てると非常に大きく成長します。そのため、地植えでバラを育てる際は、苗と苗の距離を1mほど空けて植えるようにしましょう。つるバラの場合は、2mほど空けることをおすすめします。
間隔を空けずに植えてしまうと、大きくなるにつれバラ同士がぶつかり、世話がしにくくなるため注意しましょう。また、風通しが悪くなるため病気にもかかりやすくなります。
土を入れ替える
バラを植える前に、土をバラ栽培に適したものに入れ替えます。土は保水力があり、水はけと通気性が良いものを選んでください。
初心者の方はバラ専用の培養土を購入するのがおすすめですが、自分で土を用意する場合は、完熟のたい肥を3分の1程度混ぜるとよいでしょう。
直径、深さともに50cmほどの穴を掘り、新しい土を入れていきます。バラを植えたら、接ぎ口が必ず土の上に出るようにしましょう。
マルチングを行う
マルチングとは、バラの根元の土と触れている部分を、わらや腐葉土、バークチップなどで覆うことです。根元と周囲の土を覆うと、土から水分が蒸発しすぎることや、泥が葉に飛んで起こる病気を防げます。
夏の強い日光を遮り、土の温度の上がりすぎを防ぐ効果もあります。
正しい水やりで根を鍛える
バラを育てるうえで基本となるのが、正しい水やりです。バラの水やりは、基本的に朝のうちに行いましょう。
毎日行うのではなく、土の表面が乾いたときにたっぷり水やりをするのがポイントです。毎日少しずつ水を与えて常に湿らせた状態だと、なかなか根が伸びていきません。土の中の水分量が多い状態と乾燥した状態を繰り返すことで、バラの根が鍛えられます。
とはいえ、植えた直後はまだしっかり根付いていないため、2日に1回程度は水を与えたほうがよいでしょう。2週間ほど経ったら3日に1回、さらに2週間後には4日に1回と、だんだん水やりの頻度を下げていきます。しっかりと根付いたら、水やりはほとんど必要なくなるでしょう。
先述したように、土から跳ね返った水が葉に付いて、バラが黒星病(黒点病)などの病気にかかってしまう可能性があります。水が跳ねないよう、優しく水やりを行いましょう。
病気に強いバラを選ぶ
バラがうまく育たないといわれる理由は黒星病の存在です。黒星病はバラの生育期に雨が多い日本では発生しやすい病気といえます。バラはこの病気に罹患すると、落葉して光合成できなくなり、生育が著しく悪化し開花しなくなり、やがて枯れてしまうこともあります。雨が当たる環境下で栽培するときは、黒星病耐性が強い品種を選ぶ必要があります。
原種系バラ(キモッコウバラ、シロモッコウバラ、ハマナシ、サンショウバラ)、木立ち性四季咲き性(セント・オブ・ヨコハマ、ラリッサ・バルコニア、ディープ・ボルドー)、半つる性(リサ・リサ、シャリマー、チェリー・ボニカ)、つる性(ローズ・ブラッシュ、ピエール・エルメ、キャメロット)、ミニチュア系(グリーンアイス)などがあります。
一方、雨避けがあるベランダでは黒星病の罹患率は減りますが、うどんこ病が発生しやすくなります。ベランダではうどんこ病耐性を持つ品種を選ぶ必要があります。
弱ったバラを回復させるためのポイント
バラを枯らさないように育てる方法を紹介してきましたが、すでに弱ってしまったバラはどうしたらよいのでしょうか。
ここからは、弱ったバラを回復させる方法やポイントを、バラの状態ごとに解説します。
バラの葉がすべて落ちた場合
バラは暑さが苦手な植物です。夏の暑さが原因で葉がほぼすべて落ち、枝だけになってしまうこともあります。
葉がほぼ落ちてしまった場合は、枝先のつぼみを切り取ってください。あくまでも枝先のみで、枝を深く切らないようにしましょう。
葉が焼けてしまった場合は、9月頃に上から4分の1程度のところで剪定し、新しく芽が出るのを待ちます。
枝の先につぼみがつかない場合
伸びた枝の先につぼみがつかないことを「ブラインド」と呼びます。気温が高すぎたり低すぎたりして、つぼみが形成されなかった場合に起こる現象です。
細くて力のない枝でも、ブラインドが起きやすいでしょう。逆に、栄養を与えすぎて枝が伸び続けた場合にも、ブラインドが起こることがあります。
花を咲かせたいのであれば、同じ株のほかの花が咲き終えた頃に、ブラインドになった枝の端をカットしてみてください。四季咲きや返り咲きのバラであれば、カットした部分から再度枝が伸びて咲く可能性があります。
花の数が少なくなってきた場合
古い枝は、花を咲かせるための十分な体力がない場合があります。古い枝をそのままにせず、株元に近い新しい枝のみ残して古い枝はカットすることで、新しい枝が出て花が咲くようになるでしょう。
完全に枯れてしまった場合
地植えのバラが完全に枯れてしまった場合、回復させることはできません。また、同じ場所で再度バラを育てるのも難しいでしょう。
地植えのバラは土の奥深くまで根付いており、その根をきれいに取り除くことは困難なためです。そこに新しいバラを植えても、古い根が邪魔をして育たないでしょう。
地植えのバラが枯れるのを防ぐアイテム
地植えのバラを枯らさずに育てる方法や、弱ったバラを回復させるポイントについて解説してきました。ここからは、バラを枯らさず丈夫に育てるためにおすすめのアイテムを紹介します。
害虫予防&退治には「ベニカXネクストスプレー」

「ベニカXネクストスプレー」は、花や庭木、野菜などに幅広く使える殺虫殺菌スプレーです。
効き目の早さが特長で、害虫をすばやく駆除します。薬への耐性がついたアブラムシやハダニなども、水あめ状の成分により物理的に捕えて逃しません。
また、ベニカXネクストスプレーの殺菌成分は、バラがかかりやすい黒星病(黒点病)やうどんこ病にも効果を発揮します。病気の発生前に散布すれば予防に、発生後に散布すれば治療として使えます。
植物の表面だけでなく内部にも殺虫成分が浸透するため、雨が降っても効き目が持続します。ノズルを切り替えることでフォーカス散布とワイド散布が選べ、逆さにしての散布も可能です。
【適用害虫】ハダニ類、アブラムシ類、アザミウマ類など
土質を改善に最適な「マイローズばらの天然有機肥料」
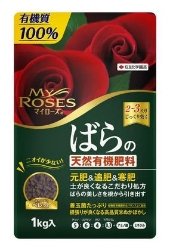
「マイローズばらの天然有機肥料」は、植物性有機質の米ぬか、おから、油粕などを使用したバラ用の肥料です。米ぬかを発酵させたものがベースとなっており、微生物や有用菌が豊富に含まれています。
手が汚れにくく使いやすいペレット状の肥料で、土に混ぜ込んだり、株元にばらまいたりして使用します。
バラの肥料として利用できるのはもちろん、継続して使うことで土質の改善にも効果を発揮します。排水性や保水性、通気性、保肥力を高め、根を張りやすい土を作ります。
なお、肥料を散布する頻度はおおよそ3ヵ月ごとに1回のペースで使用するのがおすすめです。
「マイローズばらの天然有機肥料」の詳しい商品情報や年間の施肥スケジュールはこちら>>
まとめ
バラがかかりやすい病気には、黒星病(黒点病)やうどんこ病、根頭がんしゅ病などがあり、バラに付きやすい害虫は、ハダニやアブラムシなどが挙げられます。それぞれ、特徴や対処方法が異なるため、今回紹介した内容を参考に対策してみてください。
また、ガーデニングでのバラの育て方には地植えで育てる方法と鉢植えで育てる方法があり、地植えのほうが比較的根が張って大きく育ちやすい特徴があります。地植えのバラが枯れるのを防ぐポイントと、弱ってしまったバラを回復させるポイントも紹介しているので、バラの生育に悩んでいる方はこちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。
地植えのバラを丈夫に育てるには、薬剤の使用がおすすめです。ベニカXネクストスプレーやマイローズばらの天然有機肥料、マイローズばらの肥料などを利用して、ぜひバラの栽培に挑戦してみてください。



