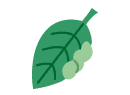葉・新芽に発生する生育不良の症状(生育が悪い、萎縮してきた、枯れてきた等)から、病原菌・害虫・ウィルス病などで考えられる原因を記載しています。
葉や新芽の症状
様々な症状がありますがその中で特に区別のつきにくい被害として、葉が食べられているのに周辺に虫の姿が見えない場合はヨトウムシ、ナメクジ、春~夏はコガネムシなど甲虫類、秋はバッタの仲間の被害が考えられます。葉色が悪いのは葉裏にハダニ、グンバイムシなどの害虫が寄生していたり、養分欠乏などの原因が考えられます。
葉に褐色などの斑点がでたり、斑点が増え続けたり拡大する場合は糸状菌(カビ)・細菌・ウイルスなどの病原菌や害虫の被害。斑点が増えたり拡大したりしない場合は薬害、日焼け、塩害などが考えられます。糸状菌による被害が大多数を占めるので、原因がよくわからない時は被害の拡大を防ぐためにもまずは糸状菌に効く殺菌剤を散布します。

-
黄色や赤く変色する(植物生理現象)、葉色が全体的にさえない
「生理障害」
-
茶色に変色する
「栽培管理」

-
細かい傷がつけられたようにみえる
「アザミウマ」

-
特に草花や野菜に被害が目立つ
「ヨトウムシ」
-
円形状に切り取られている
「ハキリバチ」
-
付近に白い粘液が付いている
-
付近に手で触れると丸くなる虫がいる
「ダンゴムシ」
-
特に花木や庭木に被害が目立つ
-
付近にコオロギやバッタなどがいる
-
葉に斑点状の小さな穴があく
「斑点性の病気」
-
蓑がぶら下がっている
「ミノムシ」
-
付近にケムシがおり、触れるとかぶれたりする
-
付近に甲虫、イモムシ状の虫がいる
「ハムシ」
「テントウムシダマシ(幼虫)」
(「コガネムシ(幼虫)」) -
付近にケムシや、アオムシ・ハバチなどのイモムシ状の虫がいる

-
葉の表面がベトベトしてくる
「カイガラムシ」

-
絵を描いたように白い筋ができる
「エカキムシ」

-
新芽や葉裏に小さい虫が群棲している
「アブラムシ」
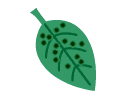
-
ススが付着したように黒くなる
「すす病」

-
葉裏に円形状に毛が生える
「赤星病」
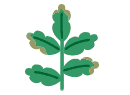
-
葉先から枯れてくる
「栽培管理」
「葉枯病」(斑点性の病気)

-
葉の緑色が濃淡のモザイク状になる
「ウイルス病」「モザイク病」